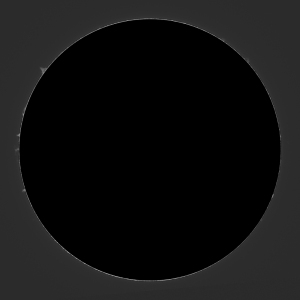満月前にふたつの彗星観察 ― 2016/05/19
昨夜は一晩中良いお天気でした。ただ、夜の時間はかなり短く、おまけに月が明け方まで残る時期です。間もなく衝を迎える火星も気になりましたが、敢えて彗星ふたつに挑戦。
まずはかなり暗くなったリニア彗星(252P)。相変わらずへびつかい座にいます。真夜中にはほぼ南中するので探しやすいですが、彗星自体はもう暗くなり、月明かりも相まって非常に見辛いものでした。10日ほど前に北上をやめ、今は南下しています。このまま暗くなるまで南下を続けるので、今が最後の見ごろでしょうか。
続いて明け方東の低空のパンスターズ彗星(C/2013X1)。明け方と言っても3時前には明るくなってくるため、かなり早くから準備しなくてはいけません。相変わらず尾が写りませんが、何人かの観測家の方がかつてのカタリナ彗星(C/2013US10)そっくりの立派に伸びた2本の尾を捉えています。
こちらもどんどん南下しているため、我が家の庭からはそろそろ限界です。月明かりが無くなる頃にちょうど光度のピークを迎えますが、その頃には完全に隣家の影。ですから、あと1、2回で見納めでしょう。
まずはかなり暗くなったリニア彗星(252P)。相変わらずへびつかい座にいます。真夜中にはほぼ南中するので探しやすいですが、彗星自体はもう暗くなり、月明かりも相まって非常に見辛いものでした。10日ほど前に北上をやめ、今は南下しています。このまま暗くなるまで南下を続けるので、今が最後の見ごろでしょうか。
続いて明け方東の低空のパンスターズ彗星(C/2013X1)。明け方と言っても3時前には明るくなってくるため、かなり早くから準備しなくてはいけません。相変わらず尾が写りませんが、何人かの観測家の方がかつてのカタリナ彗星(C/2013US10)そっくりの立派に伸びた2本の尾を捉えています。
こちらもどんどん南下しているため、我が家の庭からはそろそろ限界です。月明かりが無くなる頃にちょうど光度のピークを迎えますが、その頃には完全に隣家の影。ですから、あと1、2回で見納めでしょう。
今日の太陽 ― 2016/05/19
午後いっぱいのハロ現象 ― 2016/05/19
午前中は良く晴れていましたが、午後はゆっくり絹雲が広がり始めました。向こう一週間ほど天気の大きな崩れはないようですが、かといって快晴でもないようですね。
さて、昨日の記事でユーティリティ「太陽高度とアークの時刻表」を紹介したばかりですが、早速今日役に立ちました。今日の午後は一年の中で数回程度遭遇する「やたらハロが多い日」となったのです。以下、強調画像も併せながらご覧ください。
14:30過ぎに私用で外へ出ると、上部がやたら鮮やかな暈が見えました(左)。違和感を覚えたのでよく観察すると、内暈だけではなく別の気象光学現象が見えていたのです。暈の上側を拡大撮影したのが下左画像。なんだか虹色が二重になっていますね。これは内側が内暈、外側が外接ハロです。今日は双方とも実にはっきり分離して見えました。
徒歩移動しながらしばらく観察しましたが、ふと太陽右側にうっすらと筋状の光芒が伸びていることに気がつきました(下中画像)。この筋は太陽と同じ高さで、太陽の反対を通り越して方位角200°くらいまで見えていました。これは幻日環と呼ばれます。22°幻日、120°幻日(→2014年10月10日記事参照)ともに見えなかったのですが、幻日環だけがかなり明るく光っていました。下右画像は太陽と反対付近です。その後5分ほど経つと段々薄くなってしまいました。
その後は2時間ほど室内に入ってしまったため空の様子は分かりません。きっと色々見えたことでしょう。用事が済んで表に出るともう17時過ぎ。相変わらず内暈がクッキリ見えていました(下左画像)。他になにか見えないだろうかと目を凝らすと…あったあった!とても淡いけれど、上部ラテラルアークがグルッと見えています(下中&下右画像)。おぉ、ラテラルアークは久しぶりに見ました。なんかもう感動の連続ですね。
家に戻った頃には内暈も薄まるほど雲が厚くなっていました。早速昨日リリースした「太陽高度とアークの時刻表」で太陽高度を調べながら、HaloSimという気象光学現象シミュレーターソフトで空の様子を描いてみました。幻日環が見えていた時間の太陽高度は約44°、上部ラテラルアークが見えていたときは約18°です。それぞれの状況がよく分かりますね。実に充実した午後でした。
さて、昨日の記事でユーティリティ「太陽高度とアークの時刻表」を紹介したばかりですが、早速今日役に立ちました。今日の午後は一年の中で数回程度遭遇する「やたらハロが多い日」となったのです。以下、強調画像も併せながらご覧ください。
14:30過ぎに私用で外へ出ると、上部がやたら鮮やかな暈が見えました(左)。違和感を覚えたのでよく観察すると、内暈だけではなく別の気象光学現象が見えていたのです。暈の上側を拡大撮影したのが下左画像。なんだか虹色が二重になっていますね。これは内側が内暈、外側が外接ハロです。今日は双方とも実にはっきり分離して見えました。
徒歩移動しながらしばらく観察しましたが、ふと太陽右側にうっすらと筋状の光芒が伸びていることに気がつきました(下中画像)。この筋は太陽と同じ高さで、太陽の反対を通り越して方位角200°くらいまで見えていました。これは幻日環と呼ばれます。22°幻日、120°幻日(→2014年10月10日記事参照)ともに見えなかったのですが、幻日環だけがかなり明るく光っていました。下右画像は太陽と反対付近です。その後5分ほど経つと段々薄くなってしまいました。
その後は2時間ほど室内に入ってしまったため空の様子は分かりません。きっと色々見えたことでしょう。用事が済んで表に出るともう17時過ぎ。相変わらず内暈がクッキリ見えていました(下左画像)。他になにか見えないだろうかと目を凝らすと…あったあった!とても淡いけれど、上部ラテラルアークがグルッと見えています(下中&下右画像)。おぉ、ラテラルアークは久しぶりに見ました。なんかもう感動の連続ですね。
家に戻った頃には内暈も薄まるほど雲が厚くなっていました。早速昨日リリースした「太陽高度とアークの時刻表」で太陽高度を調べながら、HaloSimという気象光学現象シミュレーターソフトで空の様子を描いてみました。幻日環が見えていた時間の太陽高度は約44°、上部ラテラルアークが見えていたときは約18°です。それぞれの状況がよく分かりますね。実に充実した午後でした。