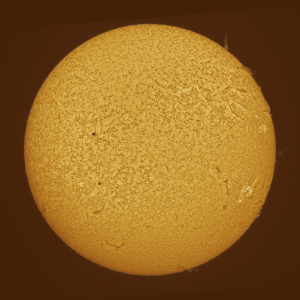テオフィルスのケモ耳 ― 2023/12/03
月は下弦に近づいています。昨夜から今朝も良く晴れて、夜半過ぎのお月見を楽しみました。
残念ながら前夜ほどシーイングは良くありませんでしたが、それでもよいときは3/10くらいになるので時々細部の観察ができました。南部(左画像)はずいぶん影が多くなり、光に紛れていた地形も見やすくなりましたね。バイイなんて満月過ぎの頃はどこなのかさっぱりでしたが、今朝はバイイの向こうにハウゼンが見えているところまで分かりました。意外にもハウゼンやドリガルスキーなどは秤動さえ良ければほぼ全体が見渡せます。
シャイナーの小さいXが暗く見えています。過渡期なのか、黒線の中にも明るい部分が混じってます。小さなX字型はそこらじゅうにあり、たとえばこの画像内なら以前にも書いたバイエルFとHが雪だるまになってる東側とか、ティコの中央丘のすぐ北東側の山頂とか、モレトスのクレーター壁内西側とかはっきり見えていますね。なにか地形上の特別な理由がある気がします。とても小さいため高倍率+好シーイングに恵まれないと観察は難しいでしょうが、挑戦してみるのも面白いでしょう。
欠け際画像も三枚掲載しておきます。下A画像はすっかり夜になった神酒の海の西側付近。驚いたことにテオフィルスの中央丘もケモ耳の影になっていました。ラングレヌスのケモ耳の完成度には負けますが、もう少し早い位相ならネコ耳になるでしょうか?こうしたケモ耳影と、クラヴィウス・アイのような光る目が組み合わさった場所は無いものでしょうか?
月探査機SLIMの飛行は順調のようですが、約1.5ヶ月後の着陸ポイント「シオリ(栞)・クレーター」はキリルスのなかです。この画像では三つの中央丘の東側、暗い谷の東に接した小さなドジョウのような形の「頭」あたりだそうです。楽しみですね。
Aの北が下B画像。静かの海で普段ほとんど確認できないラモントが、これでもかと言うほど主張していました。クラゲみたいなリッジがすごい。20本くらいの脚が生えてる?アラゴーαとβも見えてきました。良く見るとβは丸ではなく四角(台形)に広がってますね。ディオニュシウスの明るい光条と暗い光条がまだ見えます。クレーター内東側にも暗斑があるようで、下弦前の位相だとクレーター底の東が一様に明るくならず、暗い部分を伴った独特の光り方をします。
更に北へ目を移したのが下C画像。スミノルフ尾根がくっきり。バレンタイン・ドームやリンネの光条も目立ってきました。この眺めで注目したのがポシドニウスの東壁が異様に輝いていたこと。「月世界への招待」サイト・東田さんが2023年10月4日・撮影日記に書かれていたのはこのことかと思い出しました。特にここのアルベドが高いという訳ではなく、縁が光るクレーターは至るところで見つかるでしょう。
ポシドニウスやカッシニなどは内部が平坦、周囲は城郭都市の城壁のように切り立ち、しかもその壁の高さはそれほど高くありません。このため欠け際ではクレーター底が完全に暗く、低い壁だけ明るく照らされ、明暗のコントラストが強い状態です。更には壁面の法線に対して太陽の入射角と観察者への反射角がたまたま一致する(→一番明るく見える)都合の良い斜面になっているのだと考えています。ポシドニウスの北、死の湖にあるビュルクの東縁も同様に輝いていました。
もしポシドニウスが今の形状のまま月の中央にあったら壁のどの部分も位相角が0°に近づくことはありませんから、これほど明るくならない、もしくは光る面積が極端に狭いと思われます。いずれシミュレーションしてみましょう。
残念ながら前夜ほどシーイングは良くありませんでしたが、それでもよいときは3/10くらいになるので時々細部の観察ができました。南部(左画像)はずいぶん影が多くなり、光に紛れていた地形も見やすくなりましたね。バイイなんて満月過ぎの頃はどこなのかさっぱりでしたが、今朝はバイイの向こうにハウゼンが見えているところまで分かりました。意外にもハウゼンやドリガルスキーなどは秤動さえ良ければほぼ全体が見渡せます。
シャイナーの小さいXが暗く見えています。過渡期なのか、黒線の中にも明るい部分が混じってます。小さなX字型はそこらじゅうにあり、たとえばこの画像内なら以前にも書いたバイエルFとHが雪だるまになってる東側とか、ティコの中央丘のすぐ北東側の山頂とか、モレトスのクレーター壁内西側とかはっきり見えていますね。なにか地形上の特別な理由がある気がします。とても小さいため高倍率+好シーイングに恵まれないと観察は難しいでしょうが、挑戦してみるのも面白いでしょう。
欠け際画像も三枚掲載しておきます。下A画像はすっかり夜になった神酒の海の西側付近。驚いたことにテオフィルスの中央丘もケモ耳の影になっていました。ラングレヌスのケモ耳の完成度には負けますが、もう少し早い位相ならネコ耳になるでしょうか?こうしたケモ耳影と、クラヴィウス・アイのような光る目が組み合わさった場所は無いものでしょうか?
月探査機SLIMの飛行は順調のようですが、約1.5ヶ月後の着陸ポイント「シオリ(栞)・クレーター」はキリルスのなかです。この画像では三つの中央丘の東側、暗い谷の東に接した小さなドジョウのような形の「頭」あたりだそうです。楽しみですね。
Aの北が下B画像。静かの海で普段ほとんど確認できないラモントが、これでもかと言うほど主張していました。クラゲみたいなリッジがすごい。20本くらいの脚が生えてる?アラゴーαとβも見えてきました。良く見るとβは丸ではなく四角(台形)に広がってますね。ディオニュシウスの明るい光条と暗い光条がまだ見えます。クレーター内東側にも暗斑があるようで、下弦前の位相だとクレーター底の東が一様に明るくならず、暗い部分を伴った独特の光り方をします。
更に北へ目を移したのが下C画像。スミノルフ尾根がくっきり。バレンタイン・ドームやリンネの光条も目立ってきました。この眺めで注目したのがポシドニウスの東壁が異様に輝いていたこと。「月世界への招待」サイト・東田さんが2023年10月4日・撮影日記に書かれていたのはこのことかと思い出しました。特にここのアルベドが高いという訳ではなく、縁が光るクレーターは至るところで見つかるでしょう。
ポシドニウスやカッシニなどは内部が平坦、周囲は城郭都市の城壁のように切り立ち、しかもその壁の高さはそれほど高くありません。このため欠け際ではクレーター底が完全に暗く、低い壁だけ明るく照らされ、明暗のコントラストが強い状態です。更には壁面の法線に対して太陽の入射角と観察者への反射角がたまたま一致する(→一番明るく見える)都合の良い斜面になっているのだと考えています。ポシドニウスの北、死の湖にあるビュルクの東縁も同様に輝いていました。
もしポシドニウスが今の形状のまま月の中央にあったら壁のどの部分も位相角が0°に近づくことはありませんから、これほど明るくならない、もしくは光る面積が極端に狭いと思われます。いずれシミュレーションしてみましょう。