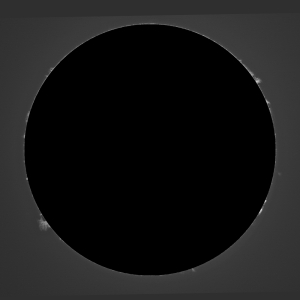月面南極域の山々 ― 2023/11/29
昨夜から今朝にかけてほとんど雲の無い星月夜でした。透明度は高いのですがシーイングは良くありません。まぁ、いつもの「冬の夜空」ですね。宵の時点で昼間の強風が続いていたため先に仮眠し、月が高くなった頃を見計らって楽しむことにしました。
望遠鏡で月面をぐるりと一周したところ、影が残る南極域の山々が目に留まりました。抜群に良い訳ではありませんが、向こう数日は月面南極を観察するのに都合が良い秤動です。LPOD・2004年1月6日記事などによると主要な山に番号が付けられているようなので、撮影画像にMナンバーを振ってみました(左画像)。M6は地球からみて南極より少し遠いため、この画像では写っていません。と言いますか、これまで少なからず撮影してきたどの画像にも写っていないようで、本当にあるのか懐疑的です。ひょっとしたら満月前後では見えず、新月前後の逆光状態でカスプにポツンと光る山なのかも知れませんね。
それぞれ高い山ですから、特に月縁近くのM3からM5は月面が半分以上欠けても見えている場合があります。例えば2023年10月6日(ほぼ下弦)のケースでは右画像のようでした。M4とM8はかなり影に入りましたが、その他はひと通り特定できます。もちろん秤動は都度変化しますから、山の重なり具合、互いの間隔などは微小に変化します。
山々の配置が立体的に感じられれば、今後注目される南極域の探査ニュースなどを耳にしたとき「あの辺りかな?」などと具体的に想像するのが楽しく思えることでしょう。非常に見辛い地域だけれど、たまにじっくり眺めて山々を訪ねるのも悪くありませんね。
そのほか、昨夜の収穫物から2枚掲載しました。下A画像はひと晩前にフンボルト連鎖クレーターを調査した付近。ペタヴィウスの右下リムに一部だけ光っている大きなクレーターがフンボルト。ほとんど夜に入りましたね。その上側、瓢箪を潰した形がヘカタイオス。縁に小クレーターが光っていますが、前日記事でC3とマークしたところです。意外に複雑な構造?(※記事下の追記参照!)前日に起伏が感じられなかったペタヴィウスも谷の影などが見えてきました。長い長いスネリウス谷も分かります。
下B画像は危難の海周辺。ちょうどガウスが明暗境界だったので構図に入れてみました。良く見るとガウスもクレーター縁に小クレーターがあるのですね。危難の海に接する位置で扇状の光条を放つプロクルスは有名ですが、危難の海内・西縁にあるリック・クレーターにも扇状の光条を放つ極小クレーターが接していて、「ミニミニ危難の海」みたい。不思議なシンメトリーを感じます(左画像・黄色矢印のところ/NASA・LROから引用)。
あちこち見ていたらいつの間にか2時間過ぎてました。手足がすっかり冷えています。防寒をしっかりしなくてはならない季節になりましたね。
望遠鏡で月面をぐるりと一周したところ、影が残る南極域の山々が目に留まりました。抜群に良い訳ではありませんが、向こう数日は月面南極を観察するのに都合が良い秤動です。LPOD・2004年1月6日記事などによると主要な山に番号が付けられているようなので、撮影画像にMナンバーを振ってみました(左画像)。M6は地球からみて南極より少し遠いため、この画像では写っていません。と言いますか、これまで少なからず撮影してきたどの画像にも写っていないようで、本当にあるのか懐疑的です。ひょっとしたら満月前後では見えず、新月前後の逆光状態でカスプにポツンと光る山なのかも知れませんね。
それぞれ高い山ですから、特に月縁近くのM3からM5は月面が半分以上欠けても見えている場合があります。例えば2023年10月6日(ほぼ下弦)のケースでは右画像のようでした。M4とM8はかなり影に入りましたが、その他はひと通り特定できます。もちろん秤動は都度変化しますから、山の重なり具合、互いの間隔などは微小に変化します。
山々の配置が立体的に感じられれば、今後注目される南極域の探査ニュースなどを耳にしたとき「あの辺りかな?」などと具体的に想像するのが楽しく思えることでしょう。非常に見辛い地域だけれど、たまにじっくり眺めて山々を訪ねるのも悪くありませんね。
そのほか、昨夜の収穫物から2枚掲載しました。下A画像はひと晩前にフンボルト連鎖クレーターを調査した付近。ペタヴィウスの右下リムに一部だけ光っている大きなクレーターがフンボルト。ほとんど夜に入りましたね。その上側、瓢箪を潰した形がヘカタイオス。縁に小クレーターが光っていますが、前日記事でC3とマークしたところです。意外に複雑な構造?(※記事下の追記参照!)前日に起伏が感じられなかったペタヴィウスも谷の影などが見えてきました。長い長いスネリウス谷も分かります。
下B画像は危難の海周辺。ちょうどガウスが明暗境界だったので構図に入れてみました。良く見るとガウスもクレーター縁に小クレーターがあるのですね。危難の海に接する位置で扇状の光条を放つプロクルスは有名ですが、危難の海内・西縁にあるリック・クレーターにも扇状の光条を放つ極小クレーターが接していて、「ミニミニ危難の海」みたい。不思議なシンメトリーを感じます(左画像・黄色矢印のところ/NASA・LROから引用)。
あちこち見ていたらいつの間にか2時間過ぎてました。手足がすっかり冷えています。防寒をしっかりしなくてはならない季節になりましたね。
【追記:アーティファクト】
上で触れたヘカタイオス・クレーター縁の小クレーターが気になったため、NASA・LRO画像などを参照したところ、こんな複雑なクレーターではない事が分かりました。
左画像は左半分が上に掲載した画像からヘカタイオスをトリミングしたもの、右半分は横長レイアウトで撮影した別ショットから切り出した同エリア。30分ほどの時間差はありますが、機材、撮り方、スタックから最終画像処理まで全く同じ行程で仕上げてあります。オレンジ矢印の小クレーターに、更に小さなクレーターのようなものがくっついていますね。これは実在しないもののようです。
レンズのゴーストやWavelet処理で発生する2重リムのように、もともと存在しないものが最終画像で発生していた場合、それをアーティファクト(人為的な偽像)などと表現します。左画像例を遡るとスタック直後の段階で既にアーティファクトが発生していました。なぜこの画像で発生したかは分かりません。
理由が何にせよ、極めて本物そっくりで見つけにくいアーティファクトですから、仕上がった結果を100%信じてはいけないことは確かです。大事な写真なら可能な限りオーバーラップして複数枚撮っておくと良いかも知れません。もっとも、これは「発生して目に見えているアーティファクト」だからまだ良いほうです。もし「画像処理段階で知らぬ間に消えてしまった」場合、見知ったエリアでない限り絶対気付けないでしょう。スタック条件によっては微小な地形や模様が消えてしまうことは、天体デジタル画像で良くあることです。
上で触れたヘカタイオス・クレーター縁の小クレーターが気になったため、NASA・LRO画像などを参照したところ、こんな複雑なクレーターではない事が分かりました。
左画像は左半分が上に掲載した画像からヘカタイオスをトリミングしたもの、右半分は横長レイアウトで撮影した別ショットから切り出した同エリア。30分ほどの時間差はありますが、機材、撮り方、スタックから最終画像処理まで全く同じ行程で仕上げてあります。オレンジ矢印の小クレーターに、更に小さなクレーターのようなものがくっついていますね。これは実在しないもののようです。
レンズのゴーストやWavelet処理で発生する2重リムのように、もともと存在しないものが最終画像で発生していた場合、それをアーティファクト(人為的な偽像)などと表現します。左画像例を遡るとスタック直後の段階で既にアーティファクトが発生していました。なぜこの画像で発生したかは分かりません。
理由が何にせよ、極めて本物そっくりで見つけにくいアーティファクトですから、仕上がった結果を100%信じてはいけないことは確かです。大事な写真なら可能な限りオーバーラップして複数枚撮っておくと良いかも知れません。もっとも、これは「発生して目に見えているアーティファクト」だからまだ良いほうです。もし「画像処理段階で知らぬ間に消えてしまった」場合、見知ったエリアでない限り絶対気付けないでしょう。スタック条件によっては微小な地形や模様が消えてしまうことは、天体デジタル画像で良くあることです。