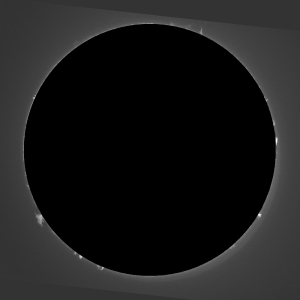今日の太陽 ― 2023/01/09
2023年のうるう秒調整はなくなりました ― 2023/01/09
今年もこの時期がやって来ました。国際地球回転・基準系事業(IERS/INTERNATIONAL EARTH ROTATION AND REFERENCE SYSTEMS SERVICE)から本日1月9日に発表された報道によると「2023年7月1日(同年6月末UT)のうるう秒挿入はない」とのことです(→IERS News:2023年1月9日UT付けBULLETIN-C65)。これにより、少なくとも今年いっぱいUTC-TAI = -37秒が維持されることが確定しました。
発表のたびに作図してきましたが、左図は2017年のうるう秒挿入直後を原点として、1日ごとのLOD(Length of Day:1日の実測長)差分値を足してゆき(水色線)、正確な時を刻む原子時計に対して自然に基づく時計がどれだけずれているか(緑線)を表したグラフ。(※測定データは昨年12月5日までを利用。)また、LODと24時間=86400秒との差の日々の値(薄青線)、および31日移動平均(赤線)をグラフ化したのが右下図です。最後にうるう秒が挿入された2017年1月8:59:60JSTから今年の正月で丸6年経ちました。今年一年間もうるう秒はありませんので、7年間うるう秒無し確定。ついに今まで最長だった1999年初めから2005年末までの「7年間うるう秒無し」に並びました。
昨年初夏に「6月29日は観測史上最短の一日」というニュースが流れたことを覚えていますか?地球自転はミリ秒単位の計測がなされている世界なので、そんななかで「最短の一日」と言われてもぴんと来なかった方がほとんどでしょう。右グラフを見ると毎年のように最短日が更新されていることが分かります。当ブログでも2022年8月17日記事で取り上げました。
最短記録並の日が今後も続くなら「地球自転は24時間より短い」ことが蓄積され、数年後に史上初の「うるう秒削除」が行われることも予期されました。でも実際はグラフの通りLODが大きくプラスに転じています。数年間様子を見なければ分かりませんが、直ちにうるう秒削除に備えなければならない、という状況は脱したように感じます。
ところで2022年11月下旬、各種メディアが一斉に「2035年までに閏秒を無くすことを決定」と報道しました。これはSI単位系を維持する国際会議「国際度量衡総会(CGPM)」が2022年11月18日に決議した事項を受けたもので、下位組織である「国際度量衡局(BIPM/Bureau international des poids et mesures)」を通じて発表された書類が公開されています。この組織名を耳にしたのは2019年5月に「キログラム原器」の廃止と国際単位系の再定義が行われて以来でしょうか。
地球自転に基づく自然時間と、原子時計によって管理された時間とのずれに関する諸問題は、閏秒導入前から長年議論の的でした。国立天文台・暦Wikiによくまとまった解説があります。閏秒があっても無くてもメリットとデメリットがあり、それ故議論は平行線のままです。
前述の「2035年までに無くす」ことは全世界の総意ではなく、主にIT業界などデメリットの多いサイドからの意見が強く働いたように思われました。コンピューター処理は「時刻の絶対性を利用した前後関係」が保証されなくてはなりません。ところが閏秒対応のソフトウェアと対応を忘れたソフトウェアが混在すると因果律が不確実になり、システムエラーが起こります。いつ閏秒が挿入/削除されるかは予測がつかないため事前の対策はできず、IT企業が眉をしかめるのも当然でしょう。とりわけ、「うるう秒挿入」なら何回か対応実績があったとしても、「うるう秒削除」は世界中のだれもが未経験。例えば8:59:58JST→9:00:00JSTのように1秒飛ばす措置をしたとき、銀行の処理システムがうるう秒削除に対応してなかったら、「9時直前に100万円送金した事実が無くなった」というようなことが起きる可能性があるわけです。
ただ、単純に「経済界が困るから」という理由だけで大きな決めごとを変更するのは望ましい形ではないでしょう。経済がいかに重要であっても、社会の一側面でしかありません。私は若いころIT業界にいたので情報処理の困難さは分かっているつもりですが、コンピューター内の時刻管理は一種のカウンター処理。1秒間の長さを変えるわけでは無いのだから、閏秒の有無に関わらず、カウント値を時刻に変換する仕組みを換えれば済む話。
天文宇宙分野でも、他天体や人工衛星など地球と関係なく動き回る物体に対して、UTやJSTなど地球上でしか意味をなさない時刻系は使わず、「地球系力学時(TDT/Terrestrial Dynamical Time)」や「太陽系力学時(TDB/Barycentric Dynamical Time)」など地球自転の変動を受けない時刻体系を築いてきました。コンピューターもそうすればいいだけの話。なにも閏秒は今始まった事ではないのに、なぜIT企業はもっと早くに業界全体で「絶対変動しないコンピューター時」といった発想をしなかったのだろうかと見通しの甘さを感じます。
自然時計は私たちの生活基盤です。もし原子時計のまま補正も無く生活を続けたら、時計は次第に地球自転の昼夜と関係ない時刻を刻むようになるでしょう。何千年先か分からないけれど、春の朝6時に日が昇る地方も、5時だったり7時だったり時計表示がズレてしまう訳です。さすがにそうなっては困るため、現在採用されている閏秒に代わって「○○分までずれたら直す」といった「閏分」や「閏時間」など大きな単位の補正方式を導入する試案も検討されるようです。誤解を恐れずに言うと、実害が出ない範囲で「ズレが出ても気にしない」、「私たちが我慢しよう」、「毎年細かく気にすることは止めよう」ということです。
いずれにしても現在の小学生が全員成人するまでに新方式が導入されます。私たち大人は一側面だけにとらわれず全体の動向を見守り、時に意見し、問題が起こらないよう自身も勉強しておかなくてはなりませんね。
参考:
日出没・暦関連の記事(ブログ内)
発表のたびに作図してきましたが、左図は2017年のうるう秒挿入直後を原点として、1日ごとのLOD(Length of Day:1日の実測長)差分値を足してゆき(水色線)、正確な時を刻む原子時計に対して自然に基づく時計がどれだけずれているか(緑線)を表したグラフ。(※測定データは昨年12月5日までを利用。)また、LODと24時間=86400秒との差の日々の値(薄青線)、および31日移動平均(赤線)をグラフ化したのが右下図です。最後にうるう秒が挿入された2017年1月8:59:60JSTから今年の正月で丸6年経ちました。今年一年間もうるう秒はありませんので、7年間うるう秒無し確定。ついに今まで最長だった1999年初めから2005年末までの「7年間うるう秒無し」に並びました。
昨年初夏に「6月29日は観測史上最短の一日」というニュースが流れたことを覚えていますか?地球自転はミリ秒単位の計測がなされている世界なので、そんななかで「最短の一日」と言われてもぴんと来なかった方がほとんどでしょう。右グラフを見ると毎年のように最短日が更新されていることが分かります。当ブログでも2022年8月17日記事で取り上げました。
最短記録並の日が今後も続くなら「地球自転は24時間より短い」ことが蓄積され、数年後に史上初の「うるう秒削除」が行われることも予期されました。でも実際はグラフの通りLODが大きくプラスに転じています。数年間様子を見なければ分かりませんが、直ちにうるう秒削除に備えなければならない、という状況は脱したように感じます。
ところで2022年11月下旬、各種メディアが一斉に「2035年までに閏秒を無くすことを決定」と報道しました。これはSI単位系を維持する国際会議「国際度量衡総会(CGPM)」が2022年11月18日に決議した事項を受けたもので、下位組織である「国際度量衡局(BIPM/Bureau international des poids et mesures)」を通じて発表された書類が公開されています。この組織名を耳にしたのは2019年5月に「キログラム原器」の廃止と国際単位系の再定義が行われて以来でしょうか。
地球自転に基づく自然時間と、原子時計によって管理された時間とのずれに関する諸問題は、閏秒導入前から長年議論の的でした。国立天文台・暦Wikiによくまとまった解説があります。閏秒があっても無くてもメリットとデメリットがあり、それ故議論は平行線のままです。
前述の「2035年までに無くす」ことは全世界の総意ではなく、主にIT業界などデメリットの多いサイドからの意見が強く働いたように思われました。コンピューター処理は「時刻の絶対性を利用した前後関係」が保証されなくてはなりません。ところが閏秒対応のソフトウェアと対応を忘れたソフトウェアが混在すると因果律が不確実になり、システムエラーが起こります。いつ閏秒が挿入/削除されるかは予測がつかないため事前の対策はできず、IT企業が眉をしかめるのも当然でしょう。とりわけ、「うるう秒挿入」なら何回か対応実績があったとしても、「うるう秒削除」は世界中のだれもが未経験。例えば8:59:58JST→9:00:00JSTのように1秒飛ばす措置をしたとき、銀行の処理システムがうるう秒削除に対応してなかったら、「9時直前に100万円送金した事実が無くなった」というようなことが起きる可能性があるわけです。
ただ、単純に「経済界が困るから」という理由だけで大きな決めごとを変更するのは望ましい形ではないでしょう。経済がいかに重要であっても、社会の一側面でしかありません。私は若いころIT業界にいたので情報処理の困難さは分かっているつもりですが、コンピューター内の時刻管理は一種のカウンター処理。1秒間の長さを変えるわけでは無いのだから、閏秒の有無に関わらず、カウント値を時刻に変換する仕組みを換えれば済む話。
天文宇宙分野でも、他天体や人工衛星など地球と関係なく動き回る物体に対して、UTやJSTなど地球上でしか意味をなさない時刻系は使わず、「地球系力学時(TDT/Terrestrial Dynamical Time)」や「太陽系力学時(TDB/Barycentric Dynamical Time)」など地球自転の変動を受けない時刻体系を築いてきました。コンピューターもそうすればいいだけの話。なにも閏秒は今始まった事ではないのに、なぜIT企業はもっと早くに業界全体で「絶対変動しないコンピューター時」といった発想をしなかったのだろうかと見通しの甘さを感じます。
自然時計は私たちの生活基盤です。もし原子時計のまま補正も無く生活を続けたら、時計は次第に地球自転の昼夜と関係ない時刻を刻むようになるでしょう。何千年先か分からないけれど、春の朝6時に日が昇る地方も、5時だったり7時だったり時計表示がズレてしまう訳です。さすがにそうなっては困るため、現在採用されている閏秒に代わって「○○分までずれたら直す」といった「閏分」や「閏時間」など大きな単位の補正方式を導入する試案も検討されるようです。誤解を恐れずに言うと、実害が出ない範囲で「ズレが出ても気にしない」、「私たちが我慢しよう」、「毎年細かく気にすることは止めよう」ということです。
いずれにしても現在の小学生が全員成人するまでに新方式が導入されます。私たち大人は一側面だけにとらわれず全体の動向を見守り、時に意見し、問題が起こらないよう自身も勉強しておかなくてはなりませんね。
参考:
日出没・暦関連の記事(ブログ内)