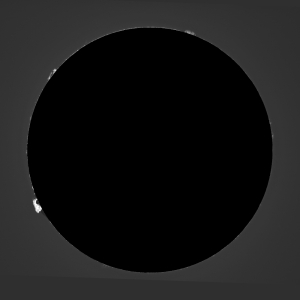束の間の月観察 ― 2023/06/30
昨夕も晴れ間はあるものの天気が不安定。あまり離れてない地域で雨や雷になっていました。日没頃に月が見えていたので観察したかったけれど天候リスクも大きい…。うーん、どうしよう…と迷ってる間に望遠鏡を組み上げてしまった。習慣ってコワイ。
西から分厚そうな雲が迫っていたので、薄暮終了を待つ暇もなく観察開始。最初は北極星がやっと見える程度の空でした。透明度もシーイングも悪く、月周囲にハロが見えており、薄雲がかかっているのは明白です。少し暗くなってから撮影開始。左画像は29日19:50過ぎの撮影で、太陽黄経差は約126.66°、撮影高度は約36.13°、月齢は11.26。
虹の入り江やJ.ハーシェル、ガッサンディ、シラーなどが朝を迎えていました。月面N地形はもう完全に日向、アリスタルコスはまだ見えません。アリスタルコス近くのハービンジャー山脈を確認、その西、かけ際に半分見えているのはクリーガーと思われます。ガッサンディから南西にヒゲのようにのびる光の筋が面白い。アヒルの親子も良く見えました。湿りの海のリッジがイイ感じ。直線壁もまだ確認できますね。
南極側の影に少し違和感を覚えました。クラヴィウス、モレトス辺りまでは良いのですが、カサトスやニュートンあたりの影が深く、この辺一体が別の大きなクレーターまたは盆地のような印象を受けました。ちょうどバイイのような…。ちなみにバイイは見える位置に来ていますがまだ夜側なので光っていません。7月に入り光を受け出す頃にはもう見える側にいない、という悲しい運命です。次に見えるのは下弦を過ぎて月が細くなるころです。ちょうど反対側のフンボルト海は今まさに見えてきたところで、満月過ぎまでこちらを向いてくれるでしょう。
撮影中に厚い雲がかかってしまったので終了。今週末は大荒れのようで、7月3日の満月も微妙です。
西から分厚そうな雲が迫っていたので、薄暮終了を待つ暇もなく観察開始。最初は北極星がやっと見える程度の空でした。透明度もシーイングも悪く、月周囲にハロが見えており、薄雲がかかっているのは明白です。少し暗くなってから撮影開始。左画像は29日19:50過ぎの撮影で、太陽黄経差は約126.66°、撮影高度は約36.13°、月齢は11.26。
虹の入り江やJ.ハーシェル、ガッサンディ、シラーなどが朝を迎えていました。月面N地形はもう完全に日向、アリスタルコスはまだ見えません。アリスタルコス近くのハービンジャー山脈を確認、その西、かけ際に半分見えているのはクリーガーと思われます。ガッサンディから南西にヒゲのようにのびる光の筋が面白い。アヒルの親子も良く見えました。湿りの海のリッジがイイ感じ。直線壁もまだ確認できますね。
南極側の影に少し違和感を覚えました。クラヴィウス、モレトス辺りまでは良いのですが、カサトスやニュートンあたりの影が深く、この辺一体が別の大きなクレーターまたは盆地のような印象を受けました。ちょうどバイイのような…。ちなみにバイイは見える位置に来ていますがまだ夜側なので光っていません。7月に入り光を受け出す頃にはもう見える側にいない、という悲しい運命です。次に見えるのは下弦を過ぎて月が細くなるころです。ちょうど反対側のフンボルト海は今まさに見えてきたところで、満月過ぎまでこちらを向いてくれるでしょう。
撮影中に厚い雲がかかってしまったので終了。今週末は大荒れのようで、7月3日の満月も微妙です。
今日の太陽とハロ現象 ― 2023/06/30
昨夕は宵のうち月が見えたものの、夜から翌朝は曇り。夜半過ぎからたまに雲のかかった晴れ間もありましたが明るい星しか見えませんでした。今朝からも雲の多い空で、午前は小雨も降りました。午後になって少しだけ青空が広がる時間があり、6月最後の太陽観察ができました。
左は14:30前の太陽。目立つ黒点を伴った活動領域13354は右半球へ。活動領域数は昨日と同じ12ヶ所です。1、2日後には半減するでしょう。昨日も見えた左下のプロミネンスは足元が光球内から生えているのがよく分かりますね。
右は太陽観察中に見えた光環。きれいな同心円状ではなく、結構乱れた感じでした。
梅雨の時期もそろそろ折り返し点。昨日は北海道と福井県で観測史上最大の降水量を記録したところがありました。今日から明日にかけても九州や四国などで線状降水帯の発生が予想されているとのこと。くれぐれもご注意ください。気象庁アメダス速報値の本日0時から15時までの集計による夏日地点数は694、真夏日地点数は120、猛暑日地点数は0でした。
左は14:30前の太陽。目立つ黒点を伴った活動領域13354は右半球へ。活動領域数は昨日と同じ12ヶ所です。1、2日後には半減するでしょう。昨日も見えた左下のプロミネンスは足元が光球内から生えているのがよく分かりますね。
右は太陽観察中に見えた光環。きれいな同心円状ではなく、結構乱れた感じでした。
梅雨の時期もそろそろ折り返し点。昨日は北海道と福井県で観測史上最大の降水量を記録したところがありました。今日から明日にかけても九州や四国などで線状降水帯の発生が予想されているとのこと。くれぐれもご注意ください。気象庁アメダス速報値の本日0時から15時までの集計による夏日地点数は694、真夏日地点数は120、猛暑日地点数は0でした。