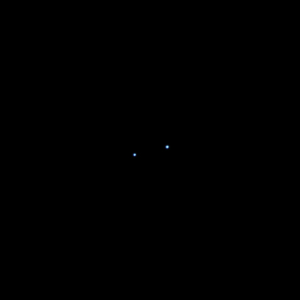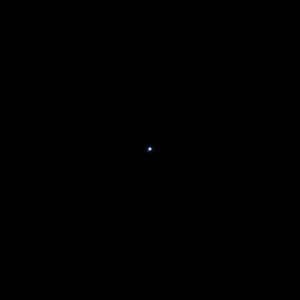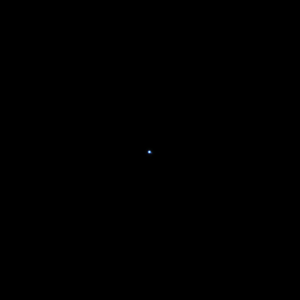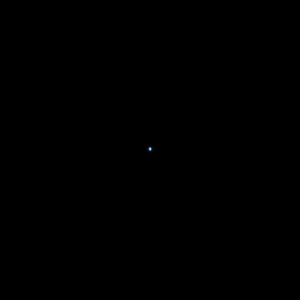束の間に見えた重星たち ― 2021/06/16
6月9日夜半から10日明け方にかけて撮影した重星画像がやっと仕上がったので掲載します。この夜は夜半前まで透明度が悪かったのですが、徐々に回復しました。気温18度台、湿度ほぼ100%で推移し、シーイングは比較的安定していました。ただ時々3m/sほどの風が吹いて望遠鏡が揺れています。
左はアルビレオ(βCyg)。明るいオレンジのA星と暗い青のB星が「見かけの」重星を成しています。どうにか色調を写し取れないか三段階露光でコンポジットしたのですが、どうしても中心部が白飛びしてしまいます。アルビレオA星のほうは実際の重星系で、いまのところAa・Ab・Acの3つで構成されていることが分かっています。AaとAbは通常の望遠鏡で分離しませんが、AaとAcは3.37等と5.16等が68.7年周期で巡り、2032年に離角0.464″まで離れますから、離角0.5″あたりを何らかの方法で光学的に分離する技術が確立できれば観測できるかも知れません。(日本のシーイングでは望み薄だけれど…可能性0%ではないと信じたい。)
観察した重星画像を下に撮影順に並べました。今回はややシビアなもの…離角1.5″以下にも挑戦しています。θSgeは6.56等の主星すぐ右上にあるB星(8.85等)のほか、右下に離れてC星(7.52等)も写っています。WDSカタログ値と比較して、位置角・離角とも異なるのでは?と思ったのが幾つかありましたが、特に4 Sgrはかなり違うようです。WDSカタログには主星4.47等、伴星8.40等、位置角243°、離角3.7″(2015年値)とありますが、どう露出設定を変えてもその位置に伴星がありません。よくよく見ると主星南側にくっつくように別の星があるような像が得られます。(もちろん色ズレ補正済み。)6年間で動いてしまった可能性もありますね。
一番最後に撮ったのは天頂近くに差し掛かるτCyg。離角1.02″は無謀だったかも知れませんが、モニター上でも撮影画像でもきちんと南北に分離しています(位置角180.4°)。北側の主星3.83等に対して南側の伴星は6.57等と暗いため、繊細な露出加減が必要でした。シーイングが良くても大雑把な撮り方では写りませんね。条件が揃えば1.0″でも分離できると分かったのは大収穫でした。おりからの天候不順に加えて明け方が早いシーズンですが、とても楽しい一夜になりました。(※掲載画像は全て画像上が天の北方向、縮尺は統一[800px四方=約200″四方相当]してあります。 )
左はアルビレオ(βCyg)。明るいオレンジのA星と暗い青のB星が「見かけの」重星を成しています。どうにか色調を写し取れないか三段階露光でコンポジットしたのですが、どうしても中心部が白飛びしてしまいます。アルビレオA星のほうは実際の重星系で、いまのところAa・Ab・Acの3つで構成されていることが分かっています。AaとAbは通常の望遠鏡で分離しませんが、AaとAcは3.37等と5.16等が68.7年周期で巡り、2032年に離角0.464″まで離れますから、離角0.5″あたりを何らかの方法で光学的に分離する技術が確立できれば観測できるかも知れません。(日本のシーイングでは望み薄だけれど…可能性0%ではないと信じたい。)
観察した重星画像を下に撮影順に並べました。今回はややシビアなもの…離角1.5″以下にも挑戦しています。θSgeは6.56等の主星すぐ右上にあるB星(8.85等)のほか、右下に離れてC星(7.52等)も写っています。WDSカタログ値と比較して、位置角・離角とも異なるのでは?と思ったのが幾つかありましたが、特に4 Sgrはかなり違うようです。WDSカタログには主星4.47等、伴星8.40等、位置角243°、離角3.7″(2015年値)とありますが、どう露出設定を変えてもその位置に伴星がありません。よくよく見ると主星南側にくっつくように別の星があるような像が得られます。(もちろん色ズレ補正済み。)6年間で動いてしまった可能性もありますね。
一番最後に撮ったのは天頂近くに差し掛かるτCyg。離角1.02″は無謀だったかも知れませんが、モニター上でも撮影画像でもきちんと南北に分離しています(位置角180.4°)。北側の主星3.83等に対して南側の伴星は6.57等と暗いため、繊細な露出加減が必要でした。シーイングが良くても大雑把な撮り方では写りませんね。条件が揃えば1.0″でも分離できると分かったのは大収穫でした。おりからの天候不順に加えて明け方が早いシーズンですが、とても楽しい一夜になりました。(※掲載画像は全て画像上が天の北方向、縮尺は統一[800px四方=約200″四方相当]してあります。 )